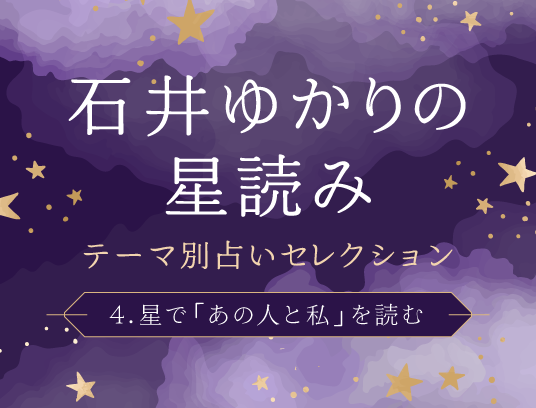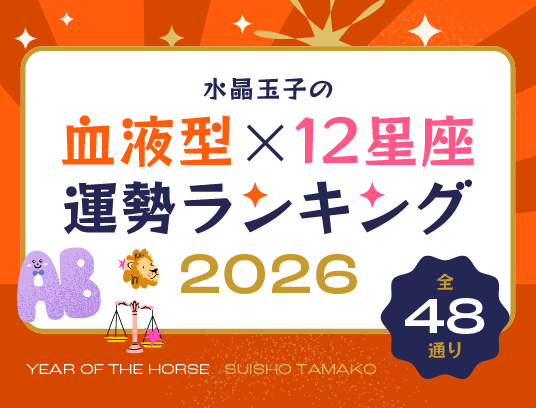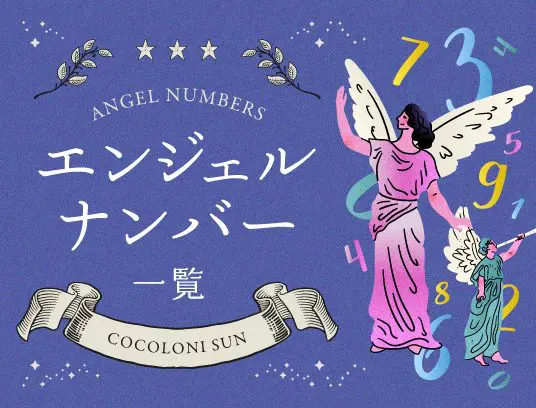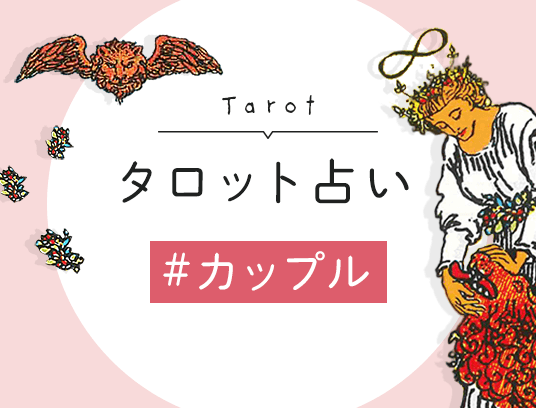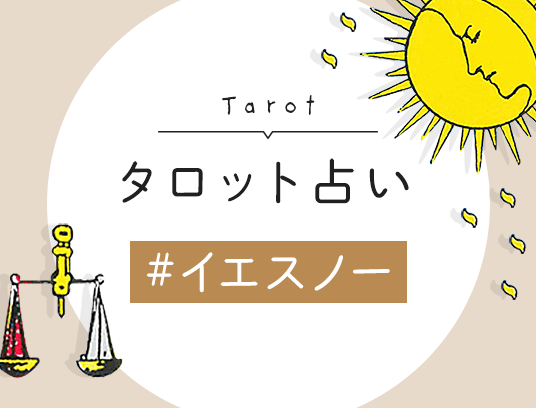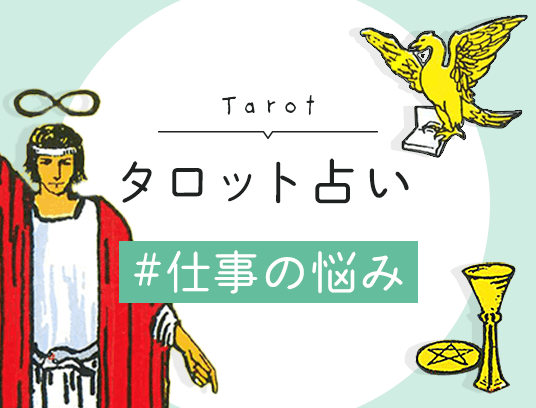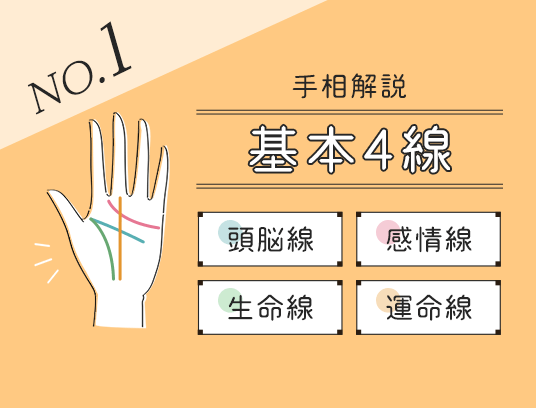石井ゆかりの幸福論【6】自分の心身に必要なこと、必要とされること。

「幸せって何だろう?」──その答えは人の数だけあるはずです。石井ゆかりさんが綴る『幸福論』で、日常の体験や思いを手がかりに、幸せのかたちをいっしょに探していきましょう。
星占いの「12ハウス」になぞらえて執筆されている本コラム。今回は第6ハウスについてです。
※このコラムは、2019年〜2021年にかけて執筆された連載に加筆・修正を加えてお届けしています。
目次
自分の心身に必要なこと、必要とされること。
「タイムスリップもの」のSFがお好きな方も多いでしょう。
私も時々、自分が遠い過去の世界に飛ばされたとしたら…、と妄想するのですが、多分、生きていけない気がするのです。
ある村にぽんと放り出されたとして、そこにいる人々は私に「おまえはどこのだれか」「どこからきたのか」と尋ねるでしょう。運よく誰かに後見してもらえるようなことがなければ、怪しいヤツとして、村からはじき出されます。他の集落に向かっても、同じようなことが起こるでしょう。街に入るには旅券のようなものが要るかもしれません。
後見者や旅券は、「縁」です。タイムスリップもののSFで、主人公は飛ばされた先で何かしら、運よく「縁」を手に入れます。運がなければ、縁なきものとして放り出され、餓死するしかないのです。
「人間は社会的存在である」という言い方があります。
血縁や地縁、身内としての愛情などの結び付きはその最たるものですが、仕事やお金を通して社会につながっている部分もあります。親として子を育てたり、親族の介護をしたりすることも、一つの「社会的結び付き」、つまり社会との「縁」と言えます。自分以外の人に対して何らかの役割を得るとき、私たちは社会につながって、そこから、生きるための血流を受け取ることができる、というイメージです。

それが得られないとき、タイムスリップで放り出された時のごとく、私たちは路頭に迷います。
「必要とされる」ことの必要性
「人の役に立ちたい」「必要とされたい」「責任を果たしたい」。
これらは、多くの人が抱く気持ちです。単なる「願い」ではなく、生きていくための切実な心の叫び、と言ってもいいかもしれません。これらの願いが叶わないとき、私たちは社会との「縁」を失い、路頭に迷って、生きていけなくなるかもしれません。
もとい、現代の日本ではだれもが、憲法により「健康で文化的な、最低限度の生活」を保証されています。それでも、そうした制度に頼ることを恥じる人が少なくありません。実際「誰からも必要とされず、誰の役にも立っていない」という思いに傷ついて、死を選ぼうとする人さえいます。
世の中から必要とされたい。他者の役に立ちたい。
こうした思いから、私たちは社会に必要とされるべく(つまり仕事を獲得すべく)、ごく若いうちから勉強し、あるいは心身を鍛える努力を重ねます。「がんばる」ことは、この世界において、とても価値あることと見なされています。
ですが、この「必要とされる」「役に立つ」ことを目指し尽くした先には、何が待っているのでしょうか。
ホロスコープで「役割・任務・就労条件」などを象徴するのが第6ハウスです。

現代的には「就労関係」がここに当てはめられるのが面白いところです。また、「病気」もこの部屋の管轄で、現代的にも「健康状態」を見る時は、6ハウスを用います。
「健康管理も仕事のうち」と言いますが、第6ハウスは継続的な労働の状態、ひいては生活のあり方や引き受けている任務の内容、任務のこなし方などを管轄しています。他者から自分に寄せられるニーズに応えることと、自分自身の心身のニーズに応えることは、強く結びついています。自分自身のニーズが満たされていなければ、他人のニーズに応えることができないからです。
「幸福」と考えたとき、まず始めに思い浮かぶのは、自分自身の心がほんわか満たされているようなイメージではないでしょうか。
では、どんなときにそんな状態になるでしょうか。
たとえば、「人のためにがんばって取り組んでいることを、『よくやっているね』『いつもありがとう』など、心から褒められ、感謝されたとき」、あたたかく充実した気持ちになるものではないでしょうか。
「人のため」と「自分のため」の配分
でも、この喜びを「追求し過ぎる」と、たいへんなことになります。たとえば「任務のためにムリやガマンをかさね、過労の果てに体を崩す」ということになってしまいます。
どんな喜びも、依存の対象となることがあります。人に褒められる喜び、人に感謝される喜びもそうです。その喜びに依存しすぎると、心身の健康をすり減らしてまで働き、自分をダメにしてしまう結果につながります。

もとい、生まれたばかりの時や介護状態では「完全に人の世話になる」ことがありますし、子どもを育てる時や職場で一大事が起こったときなどは、「完全に自分を捧げる」ような場合もあるかもしれません。そうした極端な状態は、人生の全体を覆うのではなく、人生のひとつのシーンとして体験される場合がほとんどだろうと思います。
働き過ぎの状態が続き、大きく体調を崩してしばらく休み、生き方をがらっと変えた、という人のエピソードをしばしば見かけます。これはまさに、第6ハウス内での「幸福へのシフト」です。
第6ハウスの対岸の12ハウスは「犠牲の部屋」ですが、第6ハウスは「管理の部屋」でもあります。
自分が「毎日」をどのように配分して生きるか、ということは、自らある程度以上に管理できることです。もちろん、上記のように人生の局所では、管理や調整が全く不能になることもあるでしょう。ただ、そのあとで、あるいはその前に、「自分の生きる時間をどう配分するか」は、多少は考える余地があることが多いだろうと思います。

そうならないためには、どうすればいいのか。「人から褒められ、感謝されること」に依存しすぎていないかどうか、確かめねばなりません。「人から叱られないために、嫌われないために行動する」ことも、行き過ぎると同じ結果にたどりつきます。
幸福を「調整」する
第6ハウス的な幸福は、「調整できる幸福」「工夫できる幸福」とも言えます。どの程度相手に与え、どの程度を自分に残しておくか、ということです。「自分のための自分」であることと「人のための自分」であることを両立させることも、幸福のための重要な条件です。
働き方や仕事の内容を考える時、「なにをするか」ではなく「なにをしないか」が重要だ、という考え方があります。たとえば「テレビには出ない」と決めているミュージシャンがいます。「これは自分の仕事ではない」「これは自分の責任ではない」というふうに、日々の活動に「一線を引く」ことは、とても大事なことです。
これは、第6ハウスのひとつのテーマだと思います。すなわち「なにをするか」ではなく、「なにをしないか」です。

さらに、自分で決めたことが「やっぱり、何か違うぞ」と思えたなら、これを柔軟に変えることも大切です。第6ハウスは「調整の部屋」でもあります。つねに試行錯誤し、他者と調整しながら、お互いのニーズを満たして叶う幸福が、第6ハウスのテーマです。
(2019年12月)
石井ゆかりの特別占い
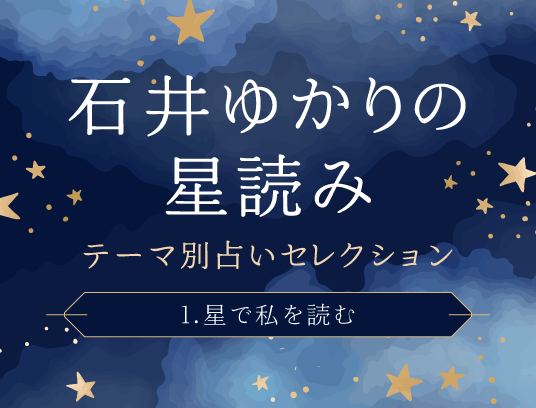
石井ゆかりの星読み テーマ別占い『星で性格を読む』
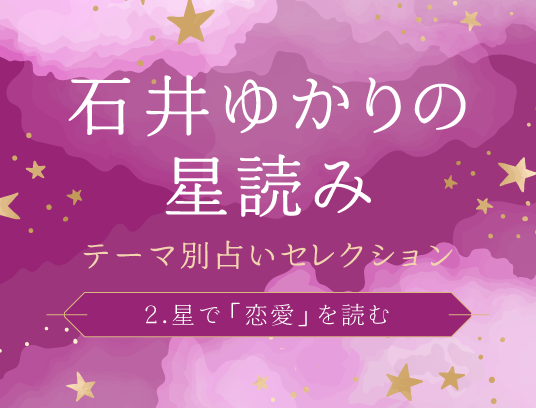
石井ゆかりの星読み テーマ別占い『星で恋愛を読む』
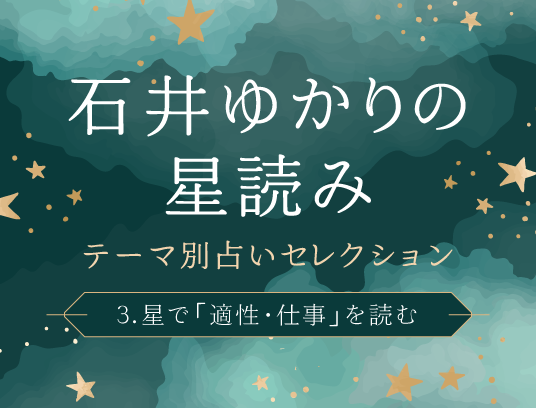
石井ゆかりの星読み テーマ別占い『星で仕事を読む』